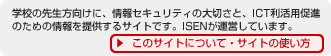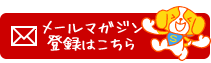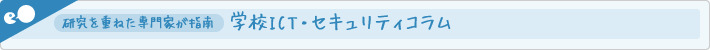2025.01.09
新たな教育の時代
今から半世紀ほど前、コンピューターの教育利用が始まった初期、
Appleコンピューターを開発したSteve Jobsは、
自ら開発したコンピューターを知の自転車「Bicycle for the mind」と名付けました。
個の理解度、学習速度に応じた指導にコンピューターを使うと同時に、
コンピューターは子供が興味関心のあることを追求する道具であるべきとの考えです。
自転車に乗れば、自分の力でどこまででも好きなところへ行くことができる。
子供たちにとってのコンピューターは、
自分の思いを形にする知の道具であるべきとの思いだと言われています。
文部科学省の、「学習指導要領の趣旨の実現に向けた
個別最適な学びと協働的な学びの一体的な充実に関する参考資料」(令和3年)では、
個別最適な学びについて「指導の個別化」と「学習の個性化」に整理されています。
指導の個別化では、子供一人一人の特性や学習進度、学習到達度等に応じ、
指導方法・教材や学習時間等の柔軟な提供・設定を行うこと。
「学習の個性化」では、子供の興味・関心・キャリア形成の方向性等に応じ、
探究において課題の設定、情報の収集、整理・分析、まとめ・表現を行う等、
教師が子供一人一人に応じた学習活動や学習課題に
取り組む機会を提供するとされています。
GIGAスクール構想で、児童・生徒が一人1台端末を持つ時代になって、
ようやくJobsの知の自転車を乗りこなす子供たちの姿が現実のものとなってきました。
みんなで自転車の楽しさを教えたいものです。
こうなると学校の教育方法も変わらざるを得ません。
一つは指導の個別化です。
個の理解度、学習速度に応じた指導にコンピューターを使うという考えは、
上述したように、コンピューターの教育利用が始まった当初から言われてきたことです。
1980年代には、児童・生徒の誤答分析やそれに基づく適切な指導助言を
する機能を持つさまざまな学習コンテンツが多くの企業で開発されました。
でもほとんど普及することはありませんでした。
教育とは、教師が児童・生徒を教えるのが基本、
コンピューターで学習なんて・・・という教育観だったのです。
確か2005年、今から20年前のことだったと記憶しています。
文部科学省の地域・学校の特色等を活かしたICT環境活用先進事例に関す
る調査研究班の座長をさせていただきました。調査報告書を2007年に書いた時です。
今と全く同じ一人1台端末を児童・生徒が持って、調べ学習をしたり、
発表したりというイラストを描かせていただきました。
まさに自律的な学びにコンピューターを活かす姿です。
報告書が発表されるや、「児童がコンピューターを持って学習するなんて・・・、
あなたは教育が分かっていない」という批判の意見をたくさんもらいました。
「皆さんにはこれがコンピューターに見えますか?これはデジタルノートです。
授業の時には子供たち皆ノートを持ってますよね。
どこが問題ですか?アナログノートに比べて、大きく写したり、
友達と意見交換したり容易にできますよ」と反論させていただいたことを思い出します。
新しい技術が教育に入るたびに、どうしても従来の価値観で皆ものを見てしまうのです。
David D.Thomburg氏の著書Edutrends2010の中に、
新しい技術が教育に持ち込まれるたびに
起こる批判的意見に関する面白い話が出てきます。
BostonカレッジのStanley Bezuska卿が過去200年にわたって調べたものだそうです。
18世紀初め、それまでの石板に変わって紙が学習に持ち込まれた時。
「石板にチョークの粉を撒き散らさないで字を書くことが
できない子供が多くなった、紙がなくなったらどうするのか」という意見が
あったといいます。
「石板の方が学習に適する、いや紙の方が・・・」という論争が
あったかどうかは定かでありませんが、
「デジタルがいい、いやアナログがいい・・・」という論争と
なんだか同じに見て取れるのです。
また、19世紀初め、インクペンが使われていた時代、
子供たちには鉛筆を削ることはできない、
ペンとインクが鉛筆に変わることはないとの話もあったといいます。
まだまだ笑えるような内容がたくさん記載されています。
M.Proustはパラダイムに関して「本当の発見とは新しい土地を見つけることではなく、
新しい目で見ることだ」と言いました。
2015年、Michael Barberは40年ギャップ説を解き、
自分たちが教育を受けたのは20年前、子供たちが実社会で活躍するのは20年後、
そこには40年のギャップが・・・と。
個人的には、もっと長く、50年、60年のギャップがあると思うのです。
時代とともに技術は変わります。技術の進化とともに、
社会の様相も変わり教育のあり方も変わるのです。
昨年末だったか、某週刊誌の「デジタル教育で日本人がバカになる」との
批判の記事が目につきました。
どうして、デジタルだアナログだと二項対立にしてしまうのか
甚だ疑問に感じたのは筆者だけではないでしょう。
批判的研究者の意見にも驚かされました。
アナログの価値観でデジタルを評価すればアナログに軍配が上がるでしょうし、
デジタルの価値観で評価すればデジタルに軍配が上がるのは当然です。
要は、既存の価値観で新しい技術を捉えるのではなく、
新しい価値観で捉えるべきではないでしょうか。
今の教育を受けている子供たちが大人になり、社会を担う人材になった時、
間違いなく言えるのはデジタル社会になっているということです。
そんな時代に求められる能力・資質を育てる教育が、今まさに始まっているのです。
GIGAスクール構想で、一人1台端末を国が準備したのは、
従来のICT活用の延長ではありません。
自律的に学ぶ子供を育てる、そのための道具なのです。
そのような学習環境のもとで教師の役割も変わります。
指導の個別化にせよ、学習の個性化にせよ、
一人一人の子供の学びに寄り添う教師の力量が求められるのは当然です。
デジタル学習環境、とりわけEdTechやYouTubeなど、
興味関心や能力に応じたデジタル・リソースの充実も進んでいます。
AI技術の教育利用も進みます。基礎基本を指導するAI教師も出てくるでしょう。
「普通の教師は言わなければならないことをしゃべる、
良い教師は分かりやすいように解説する、優れた教師は自らやってみせる、
そして、本当に偉大な教師というのは生徒の心に火をつける」
W.Arthur Wardの言葉です。
新たな教育の時代に向けて考えたいものです。

山西 潤一
富山大学 名誉教授、上越教育大学監事
日本教育情報化振興会(JAPET&CEC)会長
ICT-CONNECT 21 会長
日本教育工学協会(JAET)評議員
日本教育工学会名誉会員
一般社団法人AIイノベーション&次世代教育ネットワーク(AISEN)理事長
インターネットやコンピューターなどの情報通信技術を用いた
教育方法や学習環境の開発に関して、学校教育から生涯学習まで幅広く研究している。
専門は、教育工学、情報教育。