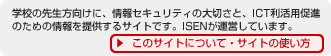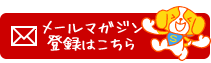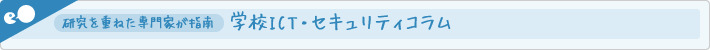2025.03.13
個別最適な学びを取り入れた授業改善について
第50回全日本教育工学研究協議会全国大会を昨年10月に終えて以降、
さまざまな自治体さまよりICTを活用した授業実践についてお問い合わせをいただき、
お話をさせていただく機会がございました。
今回は、経験豊富な授業スタイルが確立されている先生方に向けて、
個別最適な学びを取り入れることのメリットや、
効果的なICT活用方法について情報提供をさせていただきます。
個別最適な学びを実践することのメリットには、
主に①児童・生徒の可能性を制限なく伸ばすことができること、
②児童・生徒の実態に合わせた個別支援が可能となること、
③「学びに向かう力、人間性等」の育成に効果的であることの
3点が挙げられると考えています。
①については、学習指導要領に則した内容を網羅した延長線上に
教科横断型の学びや学習指導要領にとらわれない学びがあります。
そのため、前提として、教員が単元を貫いた目標設定を行うことや、
児童・生徒に単元計画(学習の進め方)を考えさせること、
さらには学習指導要領に則した単元計画になるような
教員のリードが必要であることには注意してください。
②については、一人で学習に向かうことができたり、
他者と学びを深めることができたり、児童・生徒には教員が
常に付いている必要がありません。
教員は手元の端末で児童・生徒の進捗状況を管理しながら、
一人で学習を進めることが困難な児童・生徒にアプローチすることができます。
③については、学習の進め方を自ら調整することができるよう、
発達段階に配慮をしながら指導をしていくことで、
児童・生徒は汎用性のある学び方を段階的に習得することができます。
個別最適な学びと結び付けられることが多い
「協働的な学び」と「ICTの活用」は、選択肢の1つとして考えられるべきで、
個別最適な学びを実施するために必ずしも必要ではないと考えています。
むしろ、むやみにICTを活用する授業にこだわると、
効果的でない上にICTのデメリットが際立ってしまうため、
ICTは必要に応じて活用されるべきだと強く思います。
一歩立ち止まって、「本当にICTが必要?」と問いかけてみてください。
ICTを活用することのメリットについては、
主に①可視化するためのツールであること、
②データをクラウドで管理できることの2点と考えています。
①については、児童・生徒の理解度や授業進捗状況を
可視化することができます。
真面目にノートをとり、教員の話を聞き、
発言も多い児童・生徒が、確認テストでは点数を
取れていなかった経験はありませんか。
これは、教員の想いと児童・生徒のズレが原因です。
教員はこのズレをリアルタイムで修正することができます。
②については、ノートや教科書などを持ち運ぶことから解放されるだけでなく、
教室に限定されずに学びの場を広げることができるため、
授業の可能性が広がります(不登校支援の可能性も含む)。
さらに、学習の記録を自動で残すことができるため、
自由な学びを積み重ねることや、評価もしやすくなります。
専門性のある教員がこれまで培ってきた授業スタイルは
教職員としての核であるため、否定することはしたくありません。
ただ、これからの時代を担う子供たちに携わる者として、
従来の型にとらわれるのではなく、挑戦し続け、
児童・生徒と共に学び続ける教員でありたいと私は考えています。
さらなるなる飛躍を、子供たちと共に歩んでみてはいかがでしょうか。

長谷川 正樹先生
長谷川 正樹
東京都港区立小中一貫教育校赤坂学園 主任教諭
第50回全日本教育工学研究協議会全国大会 東京都港区大会 会場校研究主任