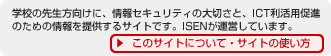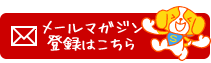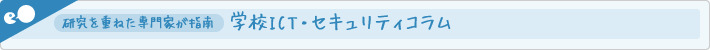2025.04.10
小・中・高等学校を通じた情報活用能力の育成
高等学校で新教科「情報」がスタートしてから約20年が経過し、
令和4年春から必修化された「情報Ⅰ」が、
令和7年度の大学入学共通テストに出題された。
共通テストへの導入は時期尚早だという声も一部から聞かれたが、
情報化やグローバル化といった社会の変化を考えれば、
情報を学ぶ重要性がますます高まっていることは明らかである。
現行の学習指導要領では、「情報活用能力」は言語能力と同様に
「学習の基盤となる資質・能力」と位置付けられている。
平成28年の中央教育審議会教育課程部会の情報ワーキンググループにおいて、
小・中・高等学校の各教科等の指導を通じて、
情報に関して身に付けることが期待される資質・能力が検討・整理され、
文字入力をはじめとする情報機器の基本的な操作技能は、
カリキュラム・マネジメントを通じて、
発達段階を踏まえ早い段階で確実に習得・適切に活用されることが示された。
つまり、小・中学校で基礎的な内容を学び、
高等学校の「情報Ⅰ」ではより高度な内容を学ぶことになったのである。
しかし、高等学校に入学してくる生徒の情報活用能力にはばらつきがあり、
期待するほど基礎・基本もできてはいないのが現状である。
地域や学校により差はあるが、小・中学校の現場では、
まず活用が先行しており、情報活用能力を体系的・計画的に
育成できているところは少ないのではないだろうか。
現職の先生方は、他の教科・科目と違って、
情報に関して小・中・高等学校で学んだ経験がほとんどない。
また、小・中学校では、各教科の学習の中で情報活用能力の育成を
進めることになっているが、高等学校の情報科のような教科はない
(中学校の技術科を除く)ため、基礎・基本を指導する体制が整いにくい。
キーボード入力の基本、情報検索や信頼性チェックの方法、
問題解決・探究の場面で情報を活用する力、
情報セキュリティを含む情報モラルなど、情報活用能力のさまざまな
要素を発達段階に応じて体系的に育成していくためには、
カリキュラム・マネジメントと、校長や教育委員会のリーダーシップが欠かせない。
そして、体系的な育成のために小・中・高等学校が連携していくことが望ましい。
私は、これまで高等学校で長く情報科教育に関わり、
ちょうどGIGAスクールがスタートした頃に中学校の校長を、
その後に高等学校の校長を務めた。
近隣の小・中学校の様子を見聞きする中で、
分かっていてもなかなか進められない現状や、
小・中学校や中・高等学校間の連携の大変さも理解している。
しかし、電子教科書の普及、生成AIの飛躍的な発展などを考えれば、
これからの学びのために情報活用能力の育成はより重要になってくる。
今後、中央教育審議会でも、GIGAスクール構想で整備された
デジタル学習基盤を前提とした学びの考え方や
情報活用能力育成の充実の在り方などが検討されるという。
次世代の子供たちのために、小・中・高等学校が互いに連携しながら
情報活用能力を育成していくことが必要ではないだろうか。

滑川先生
滑川 敬章
東京情報大学総合情報学部・教授
千葉県公立高等学校・教諭等~公立中学校・校長、県立高等学校・校長を経て現職。
高等学校の情報科教育に当初からかかわる。
文部科学省 学習指導要領等の改善に係る検討に必要な専門的作業等協力者(H27.12~H31.3)