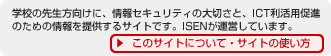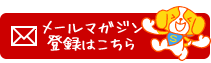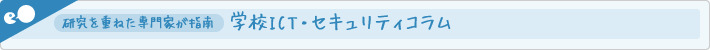2025.07.10
【インタビュー:AIが安藤先生に聞く】 AIは教育評価をどう変える?数十万体規模AIエージェントと共創する未来、問われる「人間ならではの価値」(前編)
教育の世界にも、テクノロジーの波が着実に押し寄せています。
特に「教育評価」のあり方は、
AI技術の進化とともに大きな変革期を迎えようとしています。
今回は、生成AI教育の第一人者である安藤先生のお話を基に、
教育評価の未来図と、そこで私たちが本当に大切にすべきことは何かを探ります。
◆変わり始めた教育評価の風景:「メクビット(MEXCBT)」の登場とその先
皆さんは「メクビット(MEXCBT)」という言葉を耳にしたことがあるでしょうか?
これは文部科学省が推進するCBT(Computer Based Testing)システム、
つまりコンピューターを使ったテストのことです。
安藤先生によると、すでに公立小学校の7割以上、
中学校ではほぼ100%導入されている地域もあるなど、
教育現場での活用が急速に進んでいます。
メクビット(MEXCBT)の導入は、
従来の紙テストでは難しかった多様な出題形式
(選択肢の並び替えや音声録音など)を可能にし、
教員の採点業務の負担軽減にもつながるなど、大きなメリットをもたらしています。
しかし、安藤先生は「ある特定の瞬間の学力しか
測れないという限界もある」と指摘します。
日々のコンディションや精神状態に左右される学習成果の波や、
問題バンクが固定化されることによる暗記競争への懸念、
画一的なフィードバックになりがちで深い学びにつながりにくいといった課題も、
次世代の教育評価を考える上で無視できません。
◆AIが拓く、新たな評価の地平:「長期記憶AI」と「数十万体規模AIエージェント」
では、これらの課題に対し、AIはどのような可能性を示してくれるのでしょうか?
安藤先生が注目するのは、まず「長期記憶AI」です。
これは、日々の学習活動、例えば生徒同士の対話、演習への取り組み、
探求活動のプロセスといったあらゆる学習行動を
時系列で継続的に記録・分析するAIです。
これにより、「個々の知識がどうつながり、どのように定着していくのかを
リアルタイムで見える化できる可能性がある」と安藤先生は語ります。
結果だけでなく、学びの過程そのものが評価の対象となる時代が来るかもしれません。
さらに未来的な構想として、
「数十万体規模AIエージェント」というアイデアも提示されています。
これは、それぞれが独自の目標や記憶、さらには感情のようなものを持った
AIエージェントが仮想空間上に無数に存在し、
学習者はそれらと対等に関わりながら学ぶというものです。
安藤先生はこれを「デジタルの広場(アゴラ)のようなイメージ」と表現します。
歴史上の人物を模したAIと白熱した議論を交わして交渉術を磨いたり、
仮想の市民AIと協力して都市計画をシミュレーションしたりと、
学びの形は格段に多様化し、深まることが期待されます。
◆教師の役割はどう変わるのか?評価者から「学びの設計者」へ
こうしたAI技術の進化は、教師の役割にも大きな変化を促します。
安藤先生は、「教師が評価というタスクからある程度解放されれば、
その時間をより創造的な活動に使えるようになる」と言います。
例えば、教科の枠を超えたプロジェクト学習をデザインする、
地域社会と連携したリアルな学びの場を創出する、
あるいはAIが出してきた評価が本当に妥当なのか、
教育的観点から公平なのかを吟味するといった役割です。
AIはあくまでツールであり、その活用方法を考え、
子どもたちと共に探求するファシリテーター、そして学びの場全体をデザインする
「コミュニティアーキテクト」としての教師像が浮かび上がってきます。

安藤 昇
スタディサプリ情報Ⅰ講師
青山学院大学・青山学院中等部講師
Empower Canvassador 2025
生成AI教育コンサルタント。全国の学校でDXハイスクール導入をサポート中。
スタディサプリの情報Ⅰ講師を担当し、YouTubeチャンネル「GIGAch」は登録者数3万人超。
Hulu番組「めざせ!プログラミングスター」に講師として出演。
AIと教育を組み合わせた新しい学びに挑戦しています。