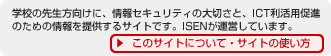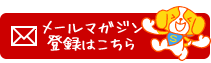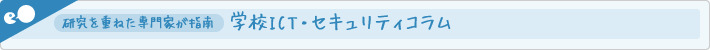2025.08.07
【インタビュー:AIが安藤先生に聞く】 AIは教育評価をどう変える?数十万体規模AIエージェントと共創する未来、問われる「人間ならではの価値」(後編)
教育の世界にも、テクノロジーの波が着実に押し寄せています。
特に「教育評価」のあり方は、AI技術の進化とともに
大きな変革期を迎えようとしています。
今回は、生成AI教育の第一人者である安藤先生のお話を基に、
教育評価の未来図と、そこで私たちが本当に大切にすべきことは何かを探ります。
◆テクノロジーの進化と倫理的課題:私たちが守るべきもの
もちろん、学習行動がすべて記録されるようになると、
プライバシーやデータの扱いといった倫理的な課題が生じます。
この点について安藤先生は、「データ主権の考え方に基づき、
学習ログは国内サーバーで厳格に管理することや、
過去の失敗から学び直す『再出発権』としてログのリセットを可能にすること、
AIの判断に疑問が生じた場合の透明性ある
『説明可能な仲裁』の仕組みなどが不可欠」と強調します。
テクノロジーの恩恵を最大限に活かしつつ、
個人の尊厳を守るためのルール作りと運用が極めて重要になります。
◆未来へのロードマップと、私たちが育むべき「人間ならではの質」
こうした未来の教育評価は、一足飛びに実現するわけではありません。
安藤先生によると、AIチューターを導入する「サンドボックス期」、
小規模なAIエージェントと討論などを行う「ハイブリッド期」、
そして最終的に数十万体規模AIエージェントが常にいるような「エコシステム期」へと、
2030年頃までを見据えた段階的な移行が想定されると考えられます
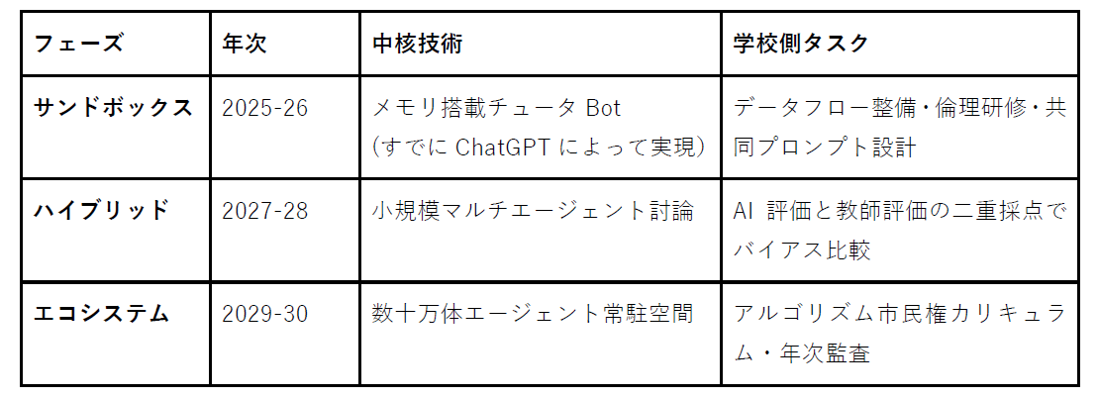
そして、最も重要なのは、
「技術が進めば進むほど、逆に人間性が問われる」という安藤先生の言葉です。
AIが知識の伝達や単純な評価を代替できるようになった時、
私たち人間、特に教育に携わる者や学ぶ者自身に求められるのは、
「人間ならではの質」です。
他者への共感力、粘り強く交渉する力、
自分自身の価値観と行動を一貫させる誠実さといった、
社会的な知性や人間性が、これからの教育評価の中心になってくるのかもしれません。
◆おわりに:あなたにとって、未来の教育で本当に大切なものは?
AIが教育評価のあり方を根本から変えようとしている今、
私たちは改めて「教育とは何か」「評価とは何のためにあるのか」を
問い直す時期に来ています。
もし将来、AIが採点のような作業を肩代わりしてくれるようになったとしたら、
教育の現場で本当に価値がある、あるいは人間ならではと評価される「質」とは、
具体的に一体どのようなものだとあなたは考えますか?
そして、そうした質を私たちはどうやって見極め、
どうやって育んでいくことになるのでしょうか?

安藤 昇
スタディサプリ情報Ⅰ講師
青山学院大学・青山学院中等部講師
Empower Canvassador 2025
生成AI教育コンサルタント。全国の学校でDXハイスクール導入をサポート中。
スタディサプリの情報Ⅰ講師を担当し、YouTubeチャンネル「GIGAch」は登録者数3万人超。
Hulu番組「めざせ!プログラミングスター」に講師として出演。
AIと教育を組み合わせた新しい学びに挑戦しています。