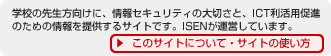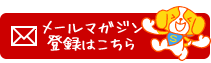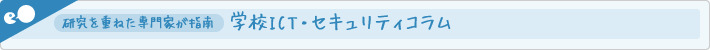2025.10.09
ロボットとEdTechがつなぐ未来の学び
韓国では近年、ロボットを使ったプログラミング教育が広がりを見せています。
「STEAM教育(科学・技術・工学・芸術・数学)」の一環として、
子供たちが自ら考え、創り出す力を育てることが重視されています。
昨年度、韓国のIBスクール(国際バカロレア認定校)で、
小学校の理科の授業を参観する機会がありました。
授業では、地震をテーマに、揺れを感知するロボットや人命救助のための
ロボットを作る活動が行われていました。
授業の冒頭では既習事項を確認し、地震に関する問題意識を持たせてから、
子供たちは各自の Chromebook でコーディングに取り組んでいました。
授業を担当した教員は大学院や研究会などでコーディングを学んだ方で、
子供たちの発想を温かく見守りながら引き出す姿が印象的でした。
ソウル市では、教育庁やIT企業が連携してロボットプログラミングを推進するほか、
「ソウルロボット人工知能科学館(Seoul Robot & AI Museum, RAIM)」のような学びの拠点も整備されています。
この科学館では、ロボットやAIに関する展示を見て学ぶだけでなく、
実際にプログラミングやロボット製作を体験できるワークショップも行われています。
学校教育と地域社会をつなぐ“未来型の学びの場”として、
多くの子供たちに人気を集めています。
また、韓国ではEdTech(教育×テクノロジー)政策も進められており、
Samsungなどが出資して設立された「Seoul EdTech SoftLab」では、
教育用ソフトの検証や開発が行われています。
ソウル市以外にも複数の都市に同様のラボがあり、
大学と連携して実証研究を行うほか、教師や保護者、開発者が意見交換を重ねながら、
学校現場に合ったEdTechの導入テストを進めています。
韓国では、大学の教員養成系学部のカリキュラムに
コーディングの授業が組み込まれており、
小学校教員も情報教育の担い手として育成されています。
こうした制度的な支えが、現場でのICT教育の充実につながっています。
日本でもプログラミング教育やICT活用が進みつつありますが、
現場では「何のために、どのように使うのか」という目的の共有が十分とはいえません。
韓国のように、学校・企業・大学・行政が協働して
学びを検証する仕組みを整えることが、
これからの教育の充実に欠かせないのではないでしょうか。
韓国のように、ロボットやAIといった“実体験を伴うICT教育”を軸に、
子供たちの創造性を育む場を地域ぐるみで整えることは、
日本の教育にとっても大きなヒントになります。
子供たちが「あったらいいな」「できたらいいな」と考えるものを、
ロボットプログラミングが形にしていく姿は、学びの未来そのものです。
大人が全てを与えるのではなく、子供自身が必要に応じてつくり出す
――そんな学びの在り方が、これからの教育に求められているのだと思います。

北島 茂樹
東京都立高等学校教諭、筑波大学附属中学校教諭を経て、現在、明星大学教授
博士(教育学,東北大学)
専門は数学教育、科学教育、教育方法学
主な著書に『未来を拓くICT教育の理論と実践』(東洋館出版社、共編著)