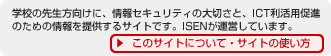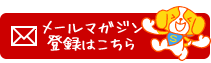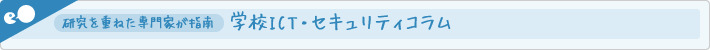2025.11.13
ICTや端末活用に関する格差の解消に向けて
GIGAスクール構想で一人1台端末になったものの、
それでみんな有効に活用できているかと言われれば、そうでもない。
本稿では、児童・生徒のICT活用や端末活用に関する格差と、
それらを解消するための方策について述べる。
〇各学校・学級によって、活用する・しないに差がある
皆さんが一番感じているのがこれだろう。
活用する・しないというより、できる・できないと言った方がよいかもしれない。
教員の活用指導力に差があるのに加え、
これまで端末がなくても授業をやってきたし、できると思っている教員が多い。
端末を活用することで、これまでできなかったことが可能になるし、負担軽減になる。
本当に便利になる。それを実感したら手放せなくなる。
各学校では、ミニ研修や情報交換会を行い、
「こうすると便利」「こうしたらうまくいった」「ちょっと教えて」を行うとよい。
校長としては、授業参観や教育委員会の視察の時に、
「必ずどこかでICTを活用するように」と言ってきた。
すると、ひとりでに教員同士の情報交換会が始まり、
学校全体に活用が広がった。
授業研究会の視点に『ICT活用』を入れるのもよい。
他の教員が活用する場面を数多く目にすることにつながるからだ。
そうすることで、次は自分も使ってみよう!と思うことにつながり、
学校全体の活用指導力の底上げが図れる。
〇経験・意識の差
端末を触り慣れている子と、そもそも触る機会が少ない子では、
当然できることに差が出る。
タイピングや検索、
ファイルの整理や作品の出来栄えなどに差が出るのは当たり前である。
家庭でのICT環境にも差があるし、
子供から端末を遠ざけたいと思っている家庭も一定数あることを考えれば、
各学校で、その差が埋められるようにする必要がある。
そのためには、端末を使う量の底上げを図れるような対策をする必要があるだろう。
毎時間、少しでも端末に触れるよう、
授業の振り返りは必ず端末で行うことも方策の一つである。
これを積み重ねることで、慣れ親しんでいく。
低学年のうちは、紙と鉛筆で書くことは大切であるが、
それと低学年のうちは端末を(あまり)使わないことは別問題である。
鉛筆で紙に書くことを大切にしながらも、端末に慣れ親しむことも大切にしてほしい。
〇管理職の意識の差
管理職(校長)がICT活用に関心が薄い場合には、
学校全体に端末活用しようという機運が盛り上がりにくい。
情報視聴覚の担当者が学校で1名や2名の学校もある。
仕事の全体量を分かっていないのだろう。
そのような場合には、ボトムアップで仕事量の全体を知らせ、
担当者を増やしてもらうように申し出るとよい。
推進する仲間が増えれば、活用が間違いなく進むからである。
端末を配当しただけでは平等にはならない。
「格差」と言われないように、常に底上げを図っていきたいものである。

阿部 千鶴
横浜市立学校の教員、横浜市教育委員会勤務をへて校長に。
北山田小学校長時代に文部科学大臣の視察を受ける。
文部科学省「学校の働き方改革」公式プロモーション動画にも出演。
現在は横浜市立荏田南小学校長。